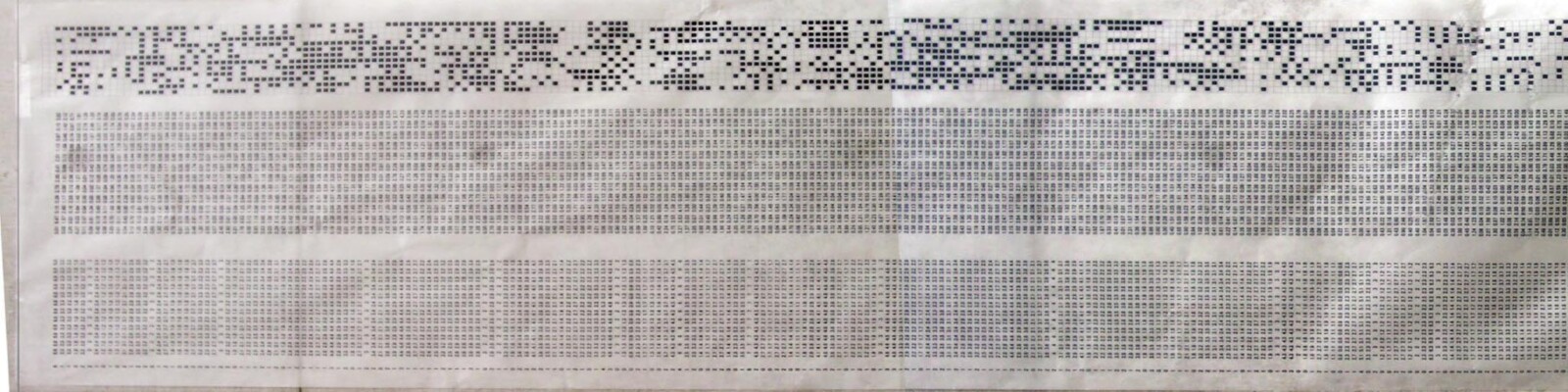このエッセイを始めるにあたっては、いささか特殊な僕の立ち位置をまず示しておくのが良いだろう。というのも、僕はこの展覧会を企画した「SETENV(現:株式会社SETENV)」の創設メンバーの一人で、アート・プロジェクト「Variations on a Silence ──リサイクル工場の現代芸術」(以下、Variations)の当事者であり、一方で現在は芸術文化を社会学的観点から論ずる研究者でもあるからだ。したがって、ここでは両者の立場を引き受けながら、16年を経過した今だからこそ浮かび上がるVariationsの輪郭の一端を記録に留めておきたい。
1. Really Volunteered ─ Variationsというコミュニティ ─
ほとんどの記憶に残るイベントがそうであったのと同様、Variationsも2000年代初頭に重なった幾つかの偶然のもとに成立していた。会場と予算は確かに株式会社リーテム(以下、リーテム)からSETENVに提供されたわけだが、今から振り返ると、展示を実装するうえで最も重要だったのは単純にマンパワーではなかっただろうか。つまり、ボランティアの存在である。
この展覧会に関わってくれたボランティアスタッフの正確な人数は記録がないのだけれども、継続的に参加してくれたスタッフが30名程度いたのだと思う。特に興味深い点はその集まり方だ。僕は主として教育普及プログラムを担当していたが、2004年の暮れには同プログラムのボランティアを募集していた。具体的には「学芸員募集の掲示板」※1にポストのうえ、応募者の面接を行った。展覧会企画の経験がない20代半ばの学生が面接をしていたというのも大概だが、結果として6名のスタッフにサポート頂くことになった。また、展示サイドでも当時運用していたSETENVの掲示板にポストしたのに加えて、初期のボランティアメンバーから口コミでコミュニティが拡がっていった。その後、半年近くボランティアスタッフの皆さんと濃密な時間を過ごしたが、大半のスタッフが何かしらの専門性を有していることに気づく。現在では、学芸員やアート・マネージャーといった専門職として活躍されている方も多い。
※1:学芸員募集の掲示板(2022年1月25日閲覧)。本稿の執筆に当たって久しぶりに掲示板を訪れたが、未だに当時のフォーマットのまま残っていることに懐かしさと同時に驚きもあった。
恐らく、このコミュニティの形成過程自体が2000年代初頭ならではのものだった。まず、展覧会のボランティアに参加するチャネルが掲示板であったことが特徴的だ。現在からは想像しづらいかもしれないが、当時は、TwitterやFacebook等のSNSを通じた情報の拡散はできない。それが意味することとは、当時はまだアートという特定の嗜好を持った人々が、その特定の嗜好に関わる専門性の高いウェブサイトを認知していて、そのサイトを自ら定期的に訪れ、情報を取得するという、ある意味では理想的なインターネット文化が残っていたということだ。その後、インターネットは、SNSによる情報の拡散やキュレーションサイトを通じて、これまでのメディアと同じようにユーザーを受け身にしていくわけだが、Variationsのスタッフは、まさにボランタリーにオンラインの情報の海から自身に必要なものを取捨選択した結果として偶然(必然か?)集まったのであり、だからこそ専門性もモチベーションも高かった。
加えて、芸術祭がまだ定着していなかった当時※2、アートセクターにおけるボランティアが制度化されていなかったことも、Variationsというコミュニティのボランタリーな性質を強めていた。美術館のボランティアは長い歴史を持つが、一方でアートセクターにおいてボランティアの存在が広く認知されていくのは、「こへび隊(大地の芸術祭)」や「こえび隊(瀬戸内芸術祭)」に代表されるように、芸術祭においてボランティアが組織化されて以降のことだ。そこには、現在の日本のアート業界が抱え込むやりがい搾取の一端もまた着床するわけだが、その制度化以前であったこともVariationsには幸いした。展覧会の企画者である僕らSETENVもまた、実質ボランティアだったことも大きいと思う。さらには、Variations全体にもそれは当てはまることで、リーテム東京工場の設計者である建築家の坂牛卓(先生)もずっと僕らの仕事をサポートしてくれていたし、リーテムの中島副社長(当時)、そして設営、撤収も含めて展覧会期間中のリーテムの社員の皆さんも、まさに「何か面白そう」という感覚からこのプロジェクトに関わっていた※3。その意味では、当時のメディア状況、および日本のアートセクターにおけるボランティアの位置づけという二つの偶然のうえに、Variationsという不思議なコミュニティが生まれたのである。
※2:本展の企画は2004年に本格化するが、当時はまだ「横浜トリエンナーレ」(2001年)や「大地の芸術祭」(2000年、2003年)が開催されていたに留まる。
※3:ただし、これはボランティアを含めたVariationsのコミュニティが理想的であったことを意味しない。「賃労働の無償化」というフレームで認定できるような搾取はなかったと思うが、一方で主としてSETENVの経験不足から、展示設営の段階で一部のスタッフに過剰な負担がかかっていた。例えば、建築学科の学生ボランティアにある展示作品の建て込みの設計が任されたり、SETENVを介さずアーティストからボランティアに直接指示が与えられる場面が存在した。
2. Fully Included ─ 芸術祭としてのVariations ─
もう一点Variationsに特徴的だったのは、「何でもあった」という点だ。これも、上述の日本における芸術祭の黎明期であったことと関わっており、展覧会としてというよりは芸術祭としての形式を備えていた点が当時としては一風変わっていた。ここで僕が、同展を「芸術祭的」と評する際の要件とは、このプロジェクトが展覧会を支える複数の形式のコンテンツで構成されていたこと、そしてそれらが地域的には分散開催されていたことだ。
まずコンテンツに関して言えば、その概要からも分かる通り、Variationsは、本体のリーテム東京工場での展覧会、ライブ・パフォーマンス、レクチャー、教育普及プログラム(ボランティアによるガイドツアー)といった、現在の芸術祭が備えるほぼすべてのコンテンツを有していた。この点は、予算規模からしても、SETENVとボランティアスタッフで構成されたある種のアマチュアの集団によるプロジェクトという特性からしても、素朴によくやったなと思う。

同時にこれらのコンテンツは、都内の異なる会場で開催されていた。展覧会本体は大田区城南島、パフォーマンスは展覧会場と代官山のライブハウスUNIT、またプレイベントとして前年の秋に刀根康尚によるレクチャーが東京大学の本郷キャンパスで行われている。展覧会の関連イベントとしてのライブ・パフォーマンス、レクチャー自体は当時も目新しいものではないが、一方で芸術祭の時代以前は、これらの関連イベントは基本的には展覧会が開催される美術館内で完結する傾向が強かった。これらのイベントがその特性に応じて、それぞれ別の場所で実施されていたこと、そして何より展示された作品群がサイトスペシフィックであったことで、都心で開催されたにもかかわらず、ある種地方で開催される芸術祭的なテイストを持っていたと考えられる。その意味では、Variationsとは芸術祭のプロトタイプのようなアート・プロジェクトでもあった※4。
※4:このように作品の鑑賞が「適度に不便であること」が、芸術祭、とりわけ日本の地域型の芸術祭の特徴でもあり、この点こそが観光のコンテンツとして人々を引き付けてきた。言い換えれば、「スタンプラリー」的なコンテンツである。
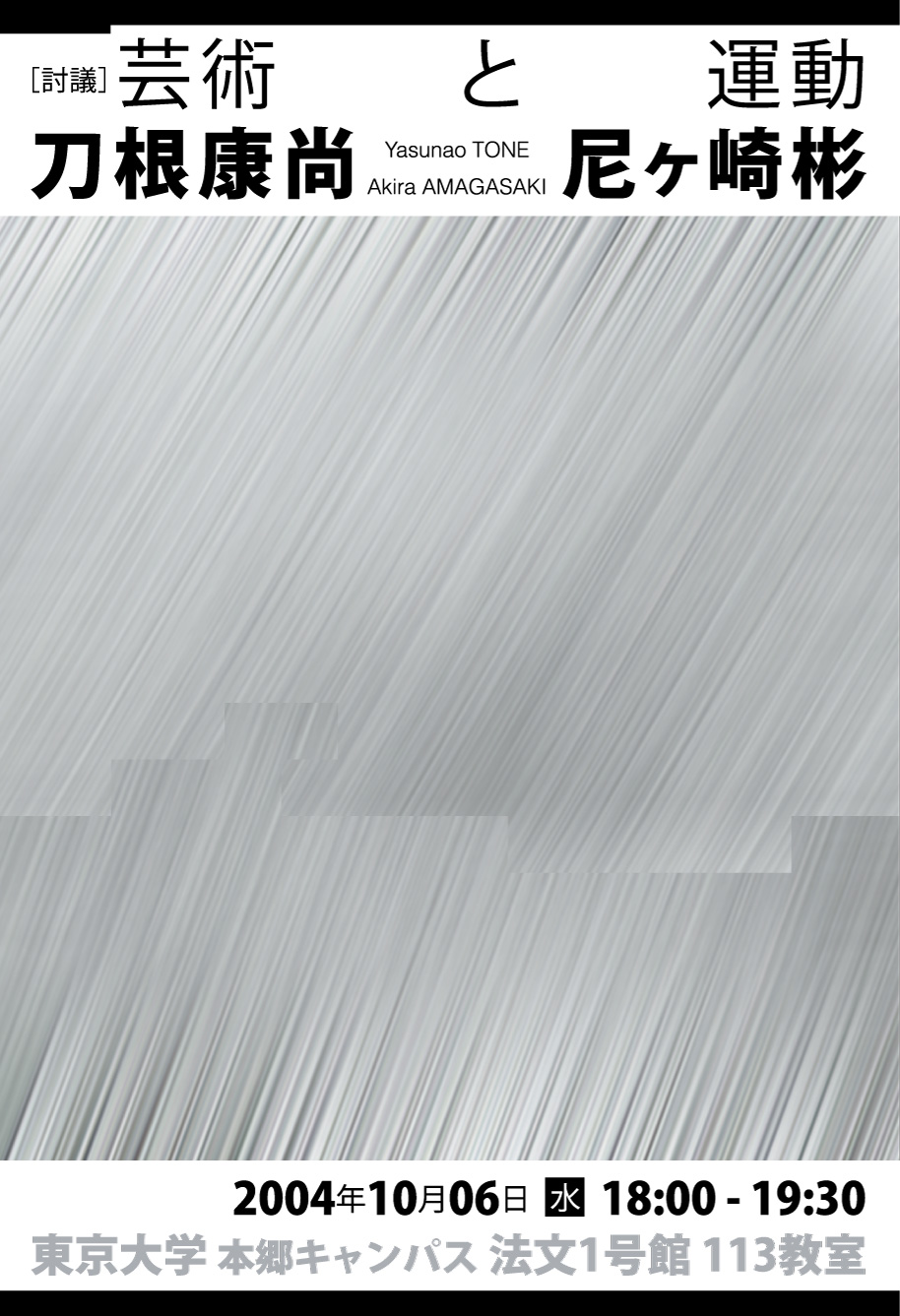
3. Somehow Marginalized ─ VariationsというDIY ─
上述のようにVariationsは、2000年代初頭という時期が可能にした複数の偶然のなかで成立したアート・プロジェクトだった。このようなボランタリーで水平性の強い人間関係のなかで、きわめてDIY的なプロセスを経て完成したのがVariationsだ。文字通り、僕らもヘルメットをかぶり、金槌を握っていたわけで。
このような環境のなかでDIY的に展覧会を作り上げることができたのは、この展覧会に関わる人々がアートセクターにおいてはある種周縁化されていたことも大きかった。僕らSETENVは、当時の20代半ばの若者としては異常にアートを見てきたと思うけれども、正規の美術教育を受けたこともなければ、Variationsこそがアートに関わる最初の大きな仕事だった※5。また、リーテムからしても、同展を一般的な意味での企業の文化事業という位置付けで開催したわけではない。さらには、この展覧会場がある城南島は、当時の石原都政の環境政策の一つ「スーパーエコタウン」の枠組みのなかで整備されたもので、後にアーツカウンシル東京へと結実するような、都の芸術文化行政の対象でもなかった。
※5:こののちSETENVは、「ネットTAM」(2004年~)や「ヨコハマ国際映像祭」(2009年)のフォーラムの運営を務めるなど、首都圏のアートワールドにおいて一定の役割を果たすと同時に、ある種の人的ハブとしても機能することになる。16年経ってVariationsを振り返るのであれば、本人たちは意識していないかもしれないが、「SETENVとは何であった/何であるのか」自体も記録の対象とする時期になっている。
このように、東京のアートワールドからは地理的にも文脈的にも周縁で自由に進められたからこそのプロジェクトがVariationsだったと思う。同時に、(予算措置や市場規模が十分ではないままに)整備されてきた現在の日本の芸術文化環境において、僕たちが今どのようにDIY的な介入ができるのかを考えるうえでも、検証されるべきケーススタディだろう。

撮影:光岡寿郎
Photography: Toshiro Mitsuoka