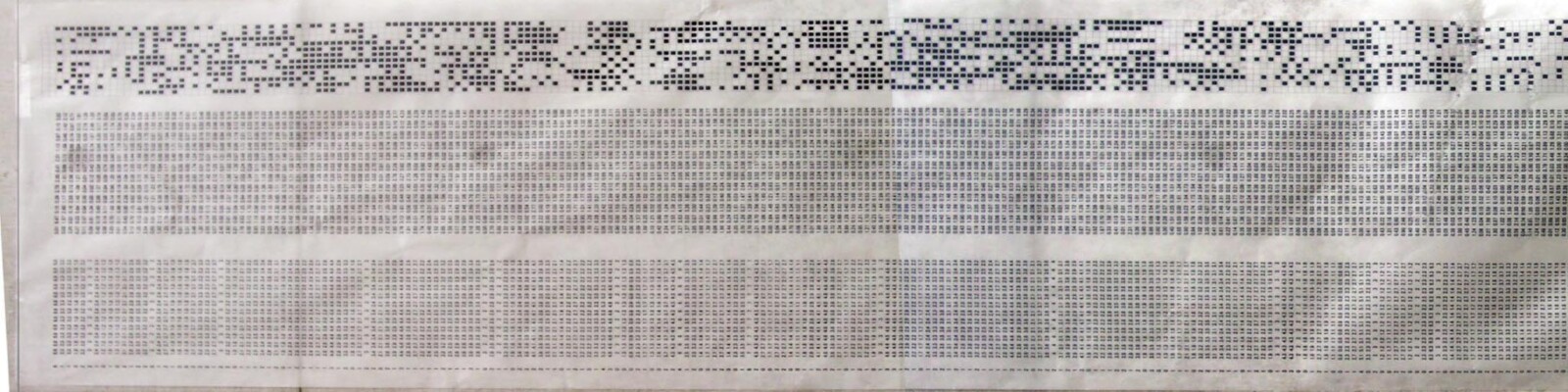羽田から飛ぶ飛行機の音が、いまも耳に残っている。
「Variations on a Silence──リサイクル工場の現代芸術」は、東京都大田区の人工島・城南島で2005年5月13日(金)から29日(日)にかけて行なわれた現代美術展である。その会場を訪れた日のことは、いまもよく覚えている。その日、わたしはJR大森駅から30分ほどバスに乗り、会場のリーテム東京工場にたどりついた。その周囲に目立った建物はほとんどなく、同じバスに乗り合わせた人々──大半がわたしと同じ20代の若者だった──の目的地がみな一緒であることは容易に察せられた。

わたしが「Variations on a Silence」について思い出そうとするとき、まず真っ先に甦ってくるのが、この会場までの道のりである。それは、都心の美術館やギャラリーに足を運ぶという日常的な経験とはまったく異なっていた。今でこそ天王州アイルをはじめ、展覧会を見るために湾岸エリアに行くのはさほど珍しいことではないが、2005年というと、現在のように湾岸エリアにスペースを構えるギャラリーもほとんど存在しなかった時代である。なおかつリーテム東京工場は、羽田空港の目と鼻の先にある。目の前に開けた広大な敷地を視野に収めつつ、天空から鳴り響く轟音を耳にしながらリサイクル工場にむかう体験は、どこか心躍るものだった。
そう、これは心躍る体験だった。それが当時のことを思い出すとき、繰り返し抱く感慨である。それは、刀根康尚、クリスチャン・マークレー、近藤一弥、ポル・マロ、710.beppo、平倉圭という、世代もバックグラウンドも異なる「Variations on a Silence」の参加アーティストについても、まったく同じことが言えた。空間的にも見どころの多いリサイクル工場で、こうした多様な作家の仕事にふれることができたのは幸運なことであったと思う。

この展覧会のことを知ったのは、いくつかの偶然による。その前年、わたしは東京大学で開講されていた坂牛卓先生(O.F.D.A.)の「建築のモノサシ」という授業に参加していた。建築について大した知識があるわけでもない不出来な学生であったわたしが、まがりなりにも半年間の授業についていけたのは、ほぼ隔週で行なわれる建築見学会という「心躍る」時間があったからだ。2005年3月に大学を卒業すると、月に一度O.F.D.A.のオフィスで開催されていた勉強会にも顔を出すようになり、エイドリアン・フォーティ『言葉と建築』(鹿島出版会、2005年)の翻訳チームの末席に加わることになった。「Variations on a Silence」のことを知ったのは、その授業の先輩にあたり、『言葉と建築』の翻訳チームのメンバーでもあったSETENVの方々を通じてであった。だから「Variations on a Silence」のことを思い出すと、それにほとんど附随するようにして、四谷三丁目のオフィスでの勉強会の記憶が甦ってくるのである。
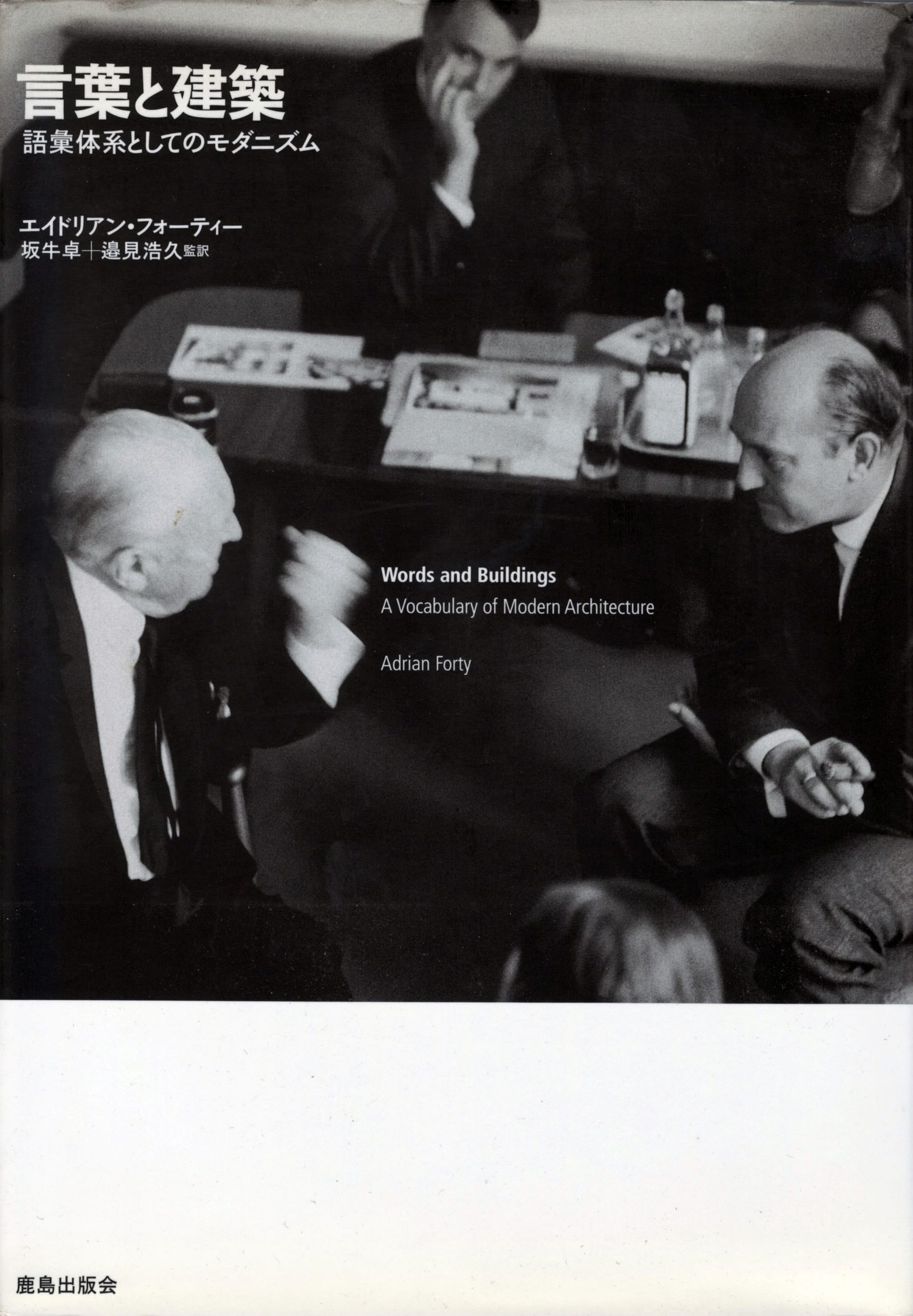
エイドリアン・フォーティ『言葉と建築 Words and Buildings -語彙体系としてのモダニズム』
翻訳:坂牛 卓+邉見 浩久/出版社:鹿島出版会/刊行年月:2006年1月/ISBN:978-4-306-04462-9 C0070
心躍る体験というのは、往々にして、そこからなにかが始まろうとする気配に包まれているものだ。「Variations on a Silence」は、すでにできあがった組織が、ありきたりのプロトコルによってつくり上げた展覧会ではない。それは、リーテム東京工場という唯一無二の場と、その設計に携わった坂牛卓先生と、展覧会を企画した若きSETENVのメンバーによってつくり上げられた、ひとつの「出来事」であったといってよい。そこで胚胎されたいくつかの可能性は、2021年に東京都現代美術館で行なわれたクリスチャン・マークレー展をはじめとする、その後のさまざまな出来事へと繋がっている。
あの日、耳に響いていた飛行機の轟音が、「到着」ではなく「出発」の印象とむすびついているのも、おそらくそのためだろう。特異な出来事というのはいつも、終わりではなく、始まりを開くものである。