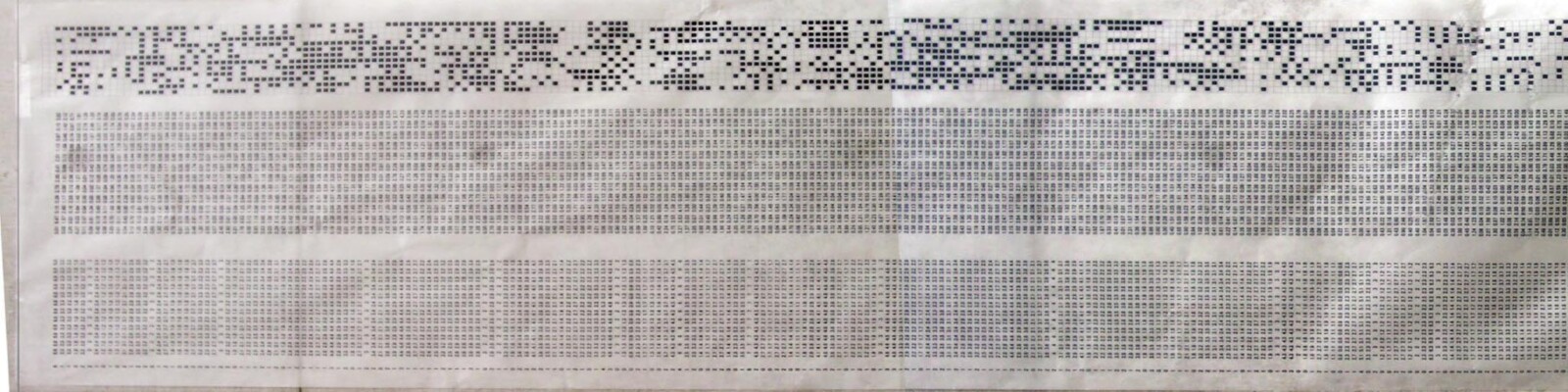1 城南島
2005年に行われた「Variations on a Silence ──リサイクル工場の現代芸術」(以下、Variations on a Silence)では、新築のリサイクル工場という環境において、そこで行われる(とはいえ稼働前なので正確には既設の工場で記録された)解体作業や発生する轟音などを素材の一つとする複数のインスタレーション作品が展開された。刀根康尚(1935−)、クリスチャン・マークレー(Christian Marclay、1955−)、近藤一弥(1960−)、ポル・マロ(Pol Malo、1967−)、710.beppo(vokoiと古舘健のユニット)、平倉圭(1977−)という、日米欧から世代間バランスが取れた出展作家の選定は、時代を先駆けていたかもしれない。これについて、17年を経た今筆者が想起するのは、会場の静謐である。そもそもイベントのタイトルに含まれる語でもあり、工場としての操業以前に開催された事情もあろうが、この印象を演出した建築的な仕掛けはもう少し手が込んでいる。
大田区城南島にあるリーテム東京工場の敷地は東京国際空港C滑走路への北側アプローチ直下にあたり、南風の季節であれば着陸機、北風の時季ならば離陸機が頻繁に上空を通過する(D滑走路は建設途上にあった)。開催は5月だったから確かに着陸機が多く、離陸機に比べれば音は小さかったかもしれない。しかし防音というごく技術的な建築性能を満たすには、建物に対して「閉じること」が様々な手段で求められるのに対し、この建物は様々な点で「開かれ」ている。
例えば正面搬入口の上部、2階をブリッジ状に渡されたオフィス空間には円筒状のヴォイドが鉛直方向に貫かれている。この円筒は、重厚なサッシで支えられた(ゆえに防音性に優れる)ガラス壁を通して、屋根で閉じられたはずの頭上をかすめるかのような航空機の影をオフィスに映し出す。ごく間近の高さなので、気づいた頃には機影は飛び去っている。機体の全長と速度については3~4両の短い新幹線がフルスピードで通過するような想像でよいので、翼の影だけが掛かった場合は文字通り一瞬である。

写真提供:O.F.D.A
室外作業場は屋根こそあるが壁のない開放的な造りで、この手の工場建築にしばしば見受ける、箱形の金属壁で全体を囲う方向性は採用されていない。上記オフィスの正面と裏面、また左方で奥行方向に延びる室内作業場の、搬出入路に向いた側の2階外壁がダブルスキンとなっている。内部壁面では人の肌から明暗をたがえて数色採られたカラースキーム、外部壁面では透明グラス、曇りグラス、窓がランダムに配置されたことで、視覚上ますます複層化し、数層のレイヤーによって被覆が硬質な印象を逃れている。この被覆全体も、山岳(筑波山?)をイメージさせる、斜線で折れた三角面によるランダムに見える組み合わせである。

写真提供:O.F.D.A
室内作業場に沿ってスリット状の水平連続窓とともに長く延びた2階通路は、内部で奥行方向のヴィスタを保証している。オフィスの下部を通過して室外作業場にアクセスする搬出入のトラックも、室外作業場の油圧ショベルで解体・選別されるリサイクル材料も、2階通路から下方に垣間見ることができる。
オフィスや2階通路から室外作業場越しに望む、空港と向かい合った海上には、別のタイミングであればB滑走路に着陸する航空機も横から眺められる。外部作業場の屋根はこの眺めを切り取るフレームとして作用している。この着陸経路は工場敷地から少し離れており、空港の展望デッキから航空機の離着陸を眺めるような距離感である。

写真提供:O.F.D.A
すなわち、物体または物質の運動、さらには視線の運動が眼前に現象していながら、音響がこれに伴わない──そのことが静謐の印象を与えるのだろう。この静謐は、音響を様々に用いたインスタレーション作品を体験する際、さらにはこの工場をとりまく物質のより大きな循環を思い描く際の素地となっていた。これが17年後の私に残響をとどめる静謐に関するラフスケッチである。
2 川崎人工島
この工場を設計した坂牛卓(1959-)は、城南島と空港を挟んで反対の南側にも自らの設計を残している。日建設計所属時のものだが(デザインには平山郁夫(1930-2009)と澄川喜一(1931-)の関与も公にされている)、東京湾アクアライン風の塔(1997供用開始)である。
海ほたるパーキングエリアより川崎側、東京湾アクアラインの全長15.1km中9.5kmを占めるアクアトンネルの建設時に、トンネル中間地点から両方向の上下線に4機のシールドマシンを掘進させるための基地として人工島が造成された。そこに、羽田空港進入路の高さ制限をクリアしながら、完成後にトンネル内部の換気を担う施設が計画された。
その造形的特徴を機能面から説明すれば、海上を南北に吹く卓越風が、異なる曲率による大小の曲面の間を通ると速度が上がる、つまり気圧が下がることを利用して、地下からスムーズに排気するというものである。風速を安定的に確保するには、地上から高く建設する方が有利である。
このことから排気を担う小塔と吸気を担う大塔の構成となり、電波の乱反射などを防ぐこと、船舶や航空機からの視認性を高めると同時に、洋上・機上から東京港・東京国際空港へのアプローチ上でシンボルとなることから、円筒にむくりをもたせて斜めにカットした形状や白と青のボーダー配色などが決定された。一方、両塔に12度の傾きが与えられたことは、機能とは関係のない造形的な操作である。
物語性の復権が図られた一面をもつポストモダニズム建築の後に、物語をほぼ語らないながら、結果的に人々の意味への想像を膨らませる造形となった。このことは、都市の入口に位置するシンボル的造形として共通する北海道百年記念塔(井口健(1938-)、1970年竣工)の能弁な物語性と対照的である。
風雪に耐えるコールテン鋼で覆われ、スムーズな輪郭と絞られた刻み目が周期的に蓄積されて、そりをもって天を突く全体が構成されたこの塔は、新千歳空港から電車で札幌市内の初めての停車駅に入るところで車窓に飛び込んでくる。設計者は入口レリーフにアイヌ民族に関わる物語を残そうとしたが「予算の都合上」実現されなかったという。
東京湾に戻ると、20階建前後のビルに相当する90m、75mという「風の塔」の高さ、いやそもそも国家的土木事業がもつ規模自体、リーテム東京工場を凌駕するものではある。しかし東京湾上に──あえてこう呼ぶならば──オブジェとして置かれたとき、特に羽田に降下中の機上から見るとその存在感は意外なほど小ぶりである。物質的な巨大さが、傾きをもって風をはらむ形態とボーダー模様という被覆により、静謐ながらも軽やかな動きに転化しているゆえであろう。
「ヨットの帆」とも形容されるこの形状は、リーテム東京工場のファサードの複層性とも対照的に、徹底的に単層の被覆、いや覆われるもののない構成にも映ずる。とはいえ、単層から複層へという坂牛の設計の歩みは、建築家としての操作の複雑化というよりは、設計者として決定できる範囲の広がりによるものと考えておきたい。また複層性と物語性は当面別のものであるが、両者の関係もいずれ考えてみたい主題である。

Nesnad, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
3 羽田空港、再び城南島
川崎人工島と城南島との間に、沖合展開事業で敷地を拡げた羽田空港でも想起したいことがある。Variations on a Silenceの4年後、2009年から翌年初頭にかけて、空港ターミナルビル内でディジタルパブリックアートの試みとして「空気の港──テクノロジー×空気で感じる新しい世界──」展が開かれたことである。アーティストの鈴木康広(1979-)が特任助教として当時在籍していた、東京大学の情報システム系研究室群の共同により、セキュリティ対策も公共性も極めて高い水準で求められる空港ターミナルビルという空間においてパブリックアートの展開を実験したプロジェクトであった。
Variations on a Silenceが、6組のアーティストと企画制作を担ったSETENVを中心に展示空間内で綿密・濃密・緊密な制作を実現させたことに比べ、大学の工学系研究室や所属学生たちを中心とした動きは、芸術的密度よりも実現・実行の面での課題解決に多大な力を割いたであろう。日本空港ビルディングや国土交通省、京浜急行電鉄など各施設管理者との調整といった実務面、また不特定多数の利用する施設における設営時間、設営と展示の条件、展示の維持といった技術面の課題である。人をくすりと微笑ませるような鈴木本来の芸術的特質もあいまって(これが作品群をパブリックにできる鍵であったろう)、両者はまるで別物にみえる。
それでも二つの展示をセットにする筆者の想起は、単に大田区や羽田空港といった地理的な近接という以上に、当時リーテム東京工場周辺にも存在した未利用地、隙間の記憶を核としている。リーテムは東京エコタウンという都有地活用事業では早期に名乗りを上げた事業者に含まれるのだろう、東京工場の竣工時に両隣はいまだ空地であった。しかし城南島に今や未利用地はないものと思われる。リーテム東京工場でも竣工と稼働開始との合間に展示が行われたのだから、これから同様の展示に向けて建物を開放する可能性は乏しい(工場見学を通じた環境教育はパンデミック後に再開されるものと思われる)。

写真提供:O.F.D.A
他方、1999年の新千歳行き全日空機ハイジャック事件、2001年のニューヨーク同時多発テロ事件は言うもおろか、2016年にも新千歳空港で保安検査すり抜け事件が起こったことなどの対応が重なり、ますます強固になる空港セキュリティが、ミュージアムと名乗る囲まれた空間を飛び出してきたパブリックアートを今も許容できるだろうか。この問いについてはかなり懐疑的にならざるを得ない。
これを言い換えるならば、パブリックアート自体が都市の隙間に寄生してきたという歴史的経緯の下で、パブリックアートの公共性と意義をめぐる本質的議論は当然必要だが、その議論は現況の社会的要請と渡り合えるのだろうか、となる。翻って考えると、株式会社リーテムや坂牛やSETENVや各アーティストなど個人のネットワークが際立ったVariations on a Silenceは、どのようなヴィジョンを掲げてどのような公共性を示したのかという問いも発生するだろう。この積極的な問いに立ち返ることが、今後の表現活動一般を支える礎になるかもしれない。
日が経ってしまったが、クリスチャン・マークレーの個展開催(「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」展、2021.11.20-2022.2.23、東京都現代美術館)を機に考え始めた本稿も、リサイクル工場の作業風景を映すモニタが円環をなす彼の作品《リサイクリング・サークル》のように、輪をなしたようである。